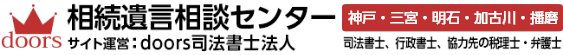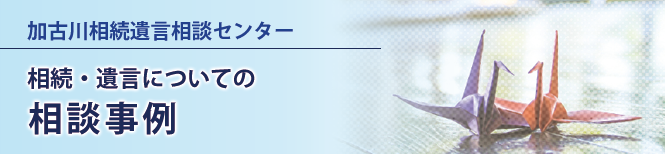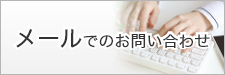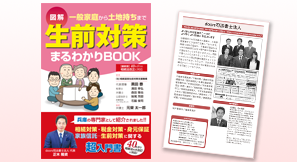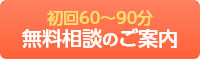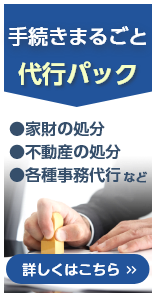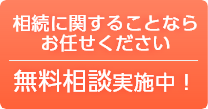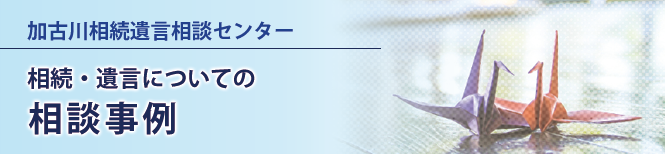
テーマ | 神戸・三宮・明石・加古川・播磨の相続なら、相続遺言相談センター - Part 7
2024年08月05日
Q:父の相続が発生しました。認知症の母が相続人なのですが、手続きの進め方を司法書士の先生に教えていただいたいです。(播磨)
播磨で母と暮らしていた父が亡くなりました。父の財産は播磨にある自宅マンションと預貯金が1000万円ほどです。相続人は母と私と妹の3人になります。母は重度の認知症を患っており、播磨の実家近くに住んでいた私も母の介護をしていました。母は署名や押印ができない状態です。この場合、相続手続きを進めることはできるのでしょうか?相続手続きを進める方法を司法書士の先生にお伺いしたいです。(播磨)
A:成年後見人を家庭裁判所で選任してもらうことで相続手続きを進めることができます。
相続人の認知症の方がいる場合、たとえご家族の方でも認知症の方に代わって署名や押印をする行為は違法となります。この場合、成年後見制度を利用することで、相続手続きを進めることができます。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を保護するための制度を成年後見制度といいます。認知症などにより判断能力が不十分である場合、法律行為を行うことはできませんので、ご本人の遺産分割を代理で行う成年後見人を定めることによって相続手続きが可能になります。
民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所が成年後見人を選任します。親族が選任されるケースもありますが、専門家が選任される場合や、複数人選任される場合もあります。ただし以下に該当する人は成年後見人にはなれません。
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 未成年者
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
家庭裁判所で選任された成年後見人は今回の相続手続きのみならず、制度の利用が継続します。その後お母様が生活していく上で必要かどうか考慮して制度を活用することをおすすめいたします。
今回のご相談者様のように相続人の中に、認知症などによって意思判断能力が不十分な方が含まれる場合には、専門家へと相談をすることをおすすめします。
播磨在住で相続についてのお困り事で悩んでいらっしゃいましたら、どのような些細な事でも構いません。ぜひ一度お気軽にお問合せください。ご相談者様のご事情をふまえ、専門家がアドバイス、サポートいたします。加古川相続遺言相談センターでは、初回のご相談は無料でお話しをお伺いさせて頂いております。
2024年07月03日
Q:遺言書の種類について司法書士の方に伺います。(加古川)
私は加古川で生まれ育った68の男性です。遺言書を作成したい理由は特にないのですが、最近テレビで遺言書を作成するといいと言っていたので興味を持ちました。実際に遺言書を作るかどうかは別として、とりあえず知識だけは入れておこうと思うので、遺言書について、特に種類などあるようでしたら教えてください。ちなみに私には2人の子供がおります。遺言書があれば子供たちが揉める事がないというのであれば作成について前向きに検討したいと思います。(加古川)
A:遺言書は複数あるためご自身に合ったものを作成しましょう。
遺言書には、ご自身の財産の分割先について記載します。相続では原則、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されるため、お子様が遺産分割で揉める恐れのある場合には作成を強くお勧めします。
特に相続財産に不動産が含まれる場合には、財産の内容が高額となるため遺言書の作成がお勧めです。相続は仲の良い親族でも揉める事があるほど繊細なシチュエーションです。遺産分割協議ではお互いの想いがぶつかり合うことになりますが、遺言書があれば遺産分割協議を行う必要がなく、相続人は遺言書の内容に沿って相続手続きを行うだけで遺産分割が済みます。ただし遺言書は遺言者が判断能力のしっかりしているうちに作成する必要がありますので、自分の意思をしっかりと反映した遺言書の作成をぜひ早急にご検討ください。
遺言書の普通方式には以下の3種類ありますのでご自身に合った方式を選ぶようにしてください。
【自筆証書遺言】 遺言者がお好きなタイミングで自筆で本文を作成し署名捺印します。財産目録は本人以外の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等を添付することも可能です。費用がかからないため人気の方式ですが、遺言の方式をチェックすることもできないため、方式の不備により無効となることもあります。また、法務局で保管していない自筆証書遺言は開封時に家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
【公正証書遺言】 遺言者が公証役場に出向いて、公証役場の公証人が遺言者から聞き取りのうえ作成します。法律家である公証人が作成するため方式の不備はありません。また原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、もっとも確実な遺言書です。ただし費用がかかります。
【秘密証書遺言】 遺言者が自分で遺言書を作成し封をしたうえで、公証役場に持ち込みます。公証人が遺言書の存在を証明します。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、ゆえに方式不備で無効となる危険性があり、費用もかかるので現在あまり使用されていません。
相続手続きの際に発生しやすいトラブルを避け、スピーディーな手続き完了を目指す加古川相続遺言相談センターでは、加古川周辺エリアの皆様の複雑な相続手続きに関するお手伝いをさせていただいております。
加古川相続遺言相談センターには、加古川の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が在籍しており、加古川の皆様の相続全般に関する疑問や不安点、難しい専門用語などについても司法書士が親身になってご対応いたします。
初回のご相談は無料ですので、加古川の皆様、ならびに加古川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。
2024年06月04日
Q:相続財産の中に不動産があるため、どのように相続手続きを進めればよいか司法書士の先生に教えていただきたい。(三宮)
はじめまして、私は三宮に暮らす40代女性です。三宮の実家に暮らしていた父が亡くなりましたので、相続手続きが必要なのですが、どのように手続きを進めればよいのかわからないのでこの度ご連絡させていただきました。
相続人となるのは母と私、そして三宮を出て都内で暮らす弟の3人です。母は役所での手続きなどに対して苦手意識が非常に強いので、基本的には私が相続手続きを進めようと思うのですが、なにぶん私も相続に関する知識がないので困っています。
特に三宮の実家については父の名義のままですので名義変更が必要だと思うのですが、手続き方法をざっとインターネットで調べただけでも複雑そうでよくわかりません。司法書士の先生、これからどのような流れで相続手続きを進めればよいか教えていただけますか。(三宮)
A:不動産を相続した際の一般的な手続き方法についてご説明いたします。
加古川相続遺言相談センターにご相談いただきありがとうございます。三宮のご相談者様のおっしゃるとおり、相続手続きは複雑なものが多く、特に不動産の相続手続きは、各ご家庭の相続のご状況によって必要書類や手順も異なってきますので、きちんと確認しながら進めていく必要があります。
こちらでは不動産の相続手続きについて、一般的な流れをご紹介させていただきます。
相続が発生した際、遺言書がない場合は被相続人(今回の相続で亡くなった方)の財産を誰がどの程度相続するかについて、遺産分割協議をもって決定することになります。遺産分割協議を終え、誰がどの財産を相続するか明確になったら、次に財産の名義変更が必要となります。
不動産については、その所有権が被相続人から相続人に移ったという手続き(所有権移転の登記)、わかりやすくいうと名義変更の手続きを行います。この手続きを終えていなければ、その不動産について第三者に主張(対抗)することができませんので、名義変更の手続きは必ず行いましょう。
【不動産の名義変更の流れ(遺言書がない場合)】
- 戸籍を収集し、法定相続人が誰になるかを確定させる。
- 相続人全員による遺産分割協議を実施。協議によって各種財産の相続先が決定したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員で署名し実印を押す。
- 名義変更の申請時に必要となる書類を準備する。
●主な必要書類……被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等、相続人全員の現在の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、不動産を相続する人の住民票、対象不動産の固定資産評価証明書、相関関係説明図 など
- 手続き時に提出する登記申請書を作成する。
- 登記申請書および必要書類を、対象の不動産の所在地を管轄する法務局へ提出する。
主な流れは以上のとおりですが、申請時に必要となる書類については相続のご状況によって異なりますのでご注意ください。また、相続人の中に未成年者や行方不明者、認知症患者などがいる場合には家庭裁判所での手続きも生じますし、被相続人が遺言書を遺していた場合は上記の流れとは異なる手続きとなります。まずは相続の専門家にご事情をお話しし、必要となる手続きを整理してみてはいかがでしょうか。
相続を専門とする司法書士であれば、上記で説明したような手続きを丸ごと代行することも可能です。特に相続した不動産の名義変更については、2024年4月より義務化されています。法務局への申請期限や罰則も設けられていますので、ご自身での手続きに不安がある場合はお早めに相続を専門とする司法書士にご相談ください。
加古川相続遺言相談センターでは三宮ならびに三宮周辺にお住いの皆様へ向けて初回無料相談の場をご用意しております。三宮での相続手続きなら、相続に関する知識と実績が豊富な加古川相続遺言相談センターの司法書士にお任せください。三宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
7 / 33«...56789...2030...»
まずはお気軽にお電話ください
0120-079-006
営業時間 9:00~20:00 [土・日・祝も相談対応]


- 足が悪い、遠方で出かけて行けない方などは、どうぞ出張相談をご利用下さい。担当者が、播磨・神戸から、無料で出張相談に対応いたします。

- 電車や公共交通機関をご利用の方は、駅まで送迎をしております。お気軽にご要望下さいませ。